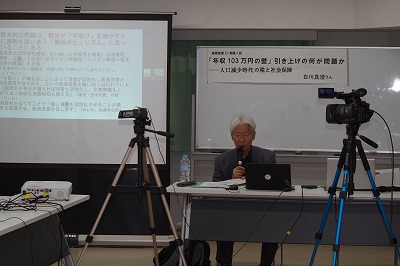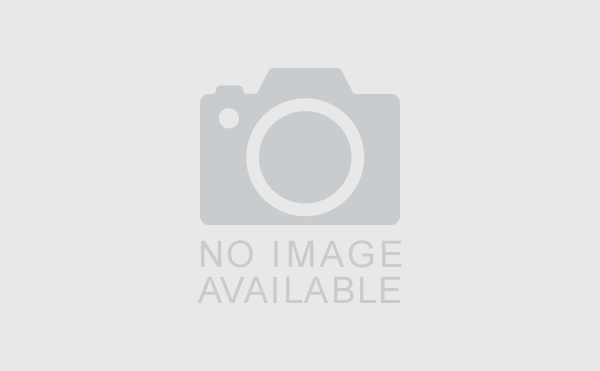座標塾第21期第1回「年収103万円の壁」引き上げの何が問題か ――人口減少時代の税と社会保障開講
3月21日、座標塾第21期第1回「年収103万円の壁」引き上げの何が問題か ――人口減少時代の税と社会保障」を開講しました。講師は白川真澄さん。
白川さんは「国民民主案は課税最低限の178万円への引き上げ。3年間の2%を超えるインフレ、実質賃金低下があり、「年収103万円の壁」引き上げ、所得税減税による「手取り」増大が歓迎・支持が強まっている。「年収の壁」引き上げは160万円でとりあえず決着した。
だが、「103万円の壁」引き上げの問題点は年収の高い人ほど優遇される不公平が発生すること。
根本的問題は、野党が「手取り」を増やすために減税を競いあう「減税ポピュリズム」に走っていること。その点はガソリン税減税も同じだ。日本のガソリン価格は米国に次いで安いのに。
野党も「手取り」が増えることによって消費が活性化し景気回復と経済成長が促される、という経済成長主義に強く囚われている。
だが、「手取り」の増大は、必ずしも個人消費の活性化につながらない。将来不安の増大と物価高があるから。
問われているのは、個人の「手取り」だけ増やす「自己責任」型社会か、税負担の引き上げで公共サービスを拡充する「連帯・助け合い」型社会かという選択肢。」
日本社会では高齢化に伴う医療や介護の費用の増大。介護の社会化が緊急の課題。労働力不足で医療・介護のニーズが満たされていない。
そして、日本社会の格差と貧困は拡大している。
にもかかわらず、「社会保障改革」では社会保障費をどう削減するかという「効率化」の議論(新自由主義)ばかりが横行している。
アベノミクスの下で、生活保護の生活扶助費の削減*医療・介護サービスの自己負担額の引き上げが行われ、マクロ経済スライドの発動で年金給付は削減される。
それなのに「防衛費」は4.7兆円05年度)から25年度は8.7兆円(歳出全体の7.5%)と急増。対中軍事包囲網の強化のために米軍のお先棒を担いでいく。
最大のムダは防衛費。「効率化」=削減は防衛費から。
公共事業関係費も削減はされたが、8兆円台を維持している。
このため、国債費の負担増が必要不可欠の財政支出を圧迫しつつある。国債費(債務償還費+利払い費)は社会保障費に次いで大きい支出で28.2兆円、歳出全体の24.4%になる。
国際比較で日本は「小さな政府」。政府支出も租税収入も大きくない。公務員数が少なく、人口1千人当たりでは欧米の半分にしかならない。
日本の税の負担率は国際比較では低い。税は軽いのになぜ重く感じているのか。
1つは社会保険料の負担が急増してきた。2つ目に税負担の不公平。税・社会保険料の負担率は、最も年収の高い層が30年間で3.7%の上昇に対して最も年収が低い層は7.8%の上昇。3つ目に政府に対する不信感が強い。
この30年間、税負担が軽くなった反面、社会保険料の負担が急上昇。社会保険料には逆進性があり、所得再分配機能が弱い。
新自由主義で大幅な減税政策を採ったにもかかわらず、経済は成長しなかった。
所得税・法人税減税によって毎年10兆円の税収が失われた。
富裕層を優遇する金融所得課税(1億円の壁)で株式の売買で大儲けする富裕層は税が軽い。
さらに欠損金繰越制度など法人税を免れるさまざまの仕組みがある。
消費税には長所と欠点があるが。最大の欠陥は、低所得者の負担率が高くなる逆進性。
税率25%のスウェーデン・ノルウェーなど消費税の高い国では社会保障が充実している。
低所得層への給付で逆進性を解消には給付付き税額控除の導入が必要だ。
「減税」だけを叫ぶポピュリズムを乗り越え、信頼できる政府の形成をめざしつつ公正な大増税で公共サービスの抜本的拡充していく必要がある。」
そして、公正な大増税として、「富裕層と大企業への課税強化から増税を始める」「ミニマム税/富裕層に対する特別の課税措置」「逆進性のある社会保険料を引き下げると同時に、累進性のある所得税の負担を引き上げる」など8つの提案を行った。
質疑応答では、今年度の予算審議の評価、社会保険料の逆進性問題、130万円の壁、男性を主な稼ぎ手とする税・社会保障モデルが未だに維持されている問題点、財政浪費としての原発、難しい税・社会保障の問題をどうやって訴えていくのか、空き家問題・持ち家制度にみられる日本の住宅政策の問題性などについて意見が出された。
白川さんは「税・社会保障の問題は難しいが、政党任せではなく、市民の立場からの議論が必要だ」と提起した。
次回第2回は「トランプ政権の再登場で世界経済はどうなるか」。講師は金子文夫さん(横浜市大名誉教授)。5月16日(金)午後6時半、文京区民センター又はZoom。