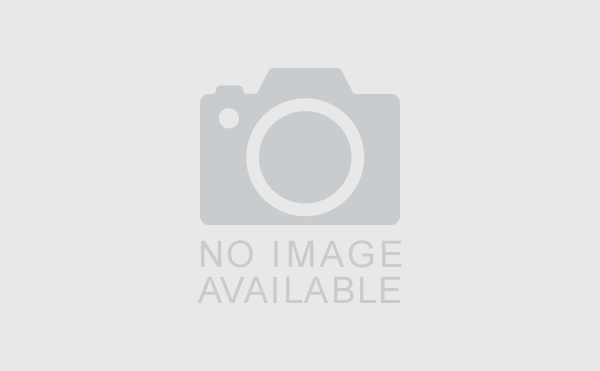座標塾第3回「フェミニズムの現在」を開講
7月18日、座標塾第21期第3回「フェミニズムの現在」を開講した。本山央子さん(アジア女性資料センター、お茶の水大学)が講演。
本山さんは「近代リベラリズムには矛盾があり、リベラリズムの基盤の「近代的個人」とは自由で平等な市民で男性。「近代的個人」の創設と同時に女性は排除され、ジェンダーは人種、階級とともに近代国家の根本的な編成原理とされながらも、「自然」「私的」なこととして非政治化される。これに対して、フェミニズムが誕生した。
第2波フェミニズムは「個人的なことは政治的なこと」と、私的・個人的は非政治的とされる側から「政治」と権力を問うた。
「ジェンダー」概念は性差の社会的構築を示す。意味は使い手によって差異がある。
グローバル・ガバナンス、女性の権利に関わる国際法制度が発展してきた。国際婦人年、世界女性会議の開催(1975~)女性差別撤廃条約(1979)など、トランスナショナルなフェミニズム運動の発展してきた。
冷戦後、あらゆるガバナンス領域に参与し影響をあたえる重要なアクターとしての「グローバル・フェミニズム」が台頭。北京女性会議(1995)はジェンダー平等を強力に推進していく主戦略として「ジェンダー主流化」を採用。政策形成・実施・評価のあらゆる段階においてジェンダー分析を導入し、政策そのものがジェンダー平等への変革効果をもつようにデザインした。
セクシュアリティ・生殖・「家族」をめぐる保守派の反発は強まり、一方で「ジェンダー」が当たり前になり、脱政治化がおきた。
日本では90年代以降、「慰安婦」、性教育へのバッシングが強まり、差別を撤廃しない男女共同参画社会基本法が作られた。「性的秩序が日本の伝統文化」という官製フェミニズムが推進された。
主流化の「成功」の帰結として、「対テロ」戦争に女性兵士が動員され、ビジネス・フェミニズムもでてきた。ジェンダーギャップ司巣を発表しているのも世界経済フォーラムだ。
N・フレイザーが言うようにフェミニズムは「資本主義の侍女」となったのか。
セクシュアリティ、あるいはポストモダニズムはグローバル資本主義の下での物質的再分配の政治という真に重要な政治的問題を覆い隠すものか。
今日は、あからさまな男性優位保守の台頭だけが脅威なのか。トランプのトランス女性排除の大統領令は白人女性が見守る中で署名された。
「フェミニズムとネオリベの共犯」を論じる左派と保守主義の共犯関係がある。ターゲットにされているのはトランスジェンダー、セックスワーク。守られるべき「ふつうの」女性(市民)という形象が作られている」
質疑応答では、左派と保守主義の共犯について、中世社会とジェンダー、ガンジーのジェンダー論。ケア労働、「反差別ワクチン」の必要性など意見が出された。
本山さんは、4月の院内集会「「生活が苦しいから税金下げろ」でいいのか?「103万円の壁」をめぐる女性と若者の声」の映像を見てほしいと紹介した。